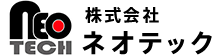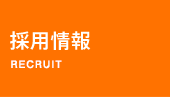INTERVEW
先輩方に協力してもらったり
助言をいただいたり
相談しやすい環境です
2022年度入社
送出技術部報道技術
担当業務
回線センター
| Q1. | 現在携わっている業務を教えてください |
| 回線センターでオペコーナー業務と無線業務に携わっています。 オペコーナー業務は海外から送られてくる伝送の映像音声連絡線の監視や民放各局との素材交換などをしています。 無線業務はNHKが管理している無線設備を使用する伝送の管理と映像音声の監視をしています。 |
| Q2. | ネオテックを志望した理由やきっかけは何ですか? |
| カメラや音声、送出など特に希望の職種はありませんでしたが、放送業界に興味があり、就職活動中は放送に携わるプロダクションなどを中心に探していました。
その中で、高専のキャリア支援室にネオテックの求人があり、NHKの技術の仕事を幅広く担っていることを知りました。 幅広いジャンルの番組を制作し、さらに放送業界の中でも特に先進的な技術を持っているNHKの業務に携われる会社なら色々なことに挑戦できると思い、ネオテックを志望しました。 |
| Q3. | 回線センターというと一般的には聞きなれない部署ですが、回線センターはどのような業務をしているのですか? |
| 日本だけではなく、世界中からNHK放送センターに伝送されるニュースやスポーツ・音楽番組等の生中継、番組制作用の素材の受信対応および、監視を行っています。 それらの回線を必要とするスタジオや制作部署に品質を保って接続することも業務のひとつです。 |

| Q4. | 回線センターに配属されて、業務への不安やプレッシャーなどはどのようなものでしたか? |
| 私は高専出身で映像について専門的に勉強をしていなかったので回線センターの業務が自分に務まるのか不安でした。研修期間に業務の研修と併せて先輩から放送や伝送についての基本的なことも教えて頂きました。回線センターの先輩は頼れる方ばかりなので、緊張感は持ちつつも気負いせずに業務にあたることができました。 |
| Q5. | 報道畑は真面目な人が多いイメージですが、実際の職場の雰囲気を教えてください |
| 実際に真面目な人は多いですが、常に張りつめた空気が流れているわけでなく業務が落ち着いていると趣味の話など色々な話をします。 また、自分の業務が輻輳しているときや分からないことがあったときに周りにいる先輩方に協力してもらったり、助言をいただいたり、相談しやすい環境です。 |
| Q6. | 回線センターは中継における司令塔の役割をしていますが、業務にあたる際心がけていることを教えてください |
| 回線センターで何か問題が起こると関係が深いニュースセンターやスタジオなど他部署にも影響がでてしまうことが多いです。 慣れている業務でもなにか違和感があったら本当にこれでいいのか確認したり、周りに相談したりして少しでも違和感を解消するようにしています。 |
| Q7. | 入社一年目にサッカーワールドカップカタール大会の伝送を任されていましたが、業務内容はどのようなものでしたか? |
| カタールとの時差の都合上、20時からの勤務で4K/2K回線の監視が業務のメインでした。
4K/2K回線を同時に受信していたため普段のスポーツ中継よりも回線数が多く、少ない人数で対応するため回線テストが大変だったことを覚えています。 ワールドカップの対応の中で初めて扱う機器があり先輩方に話を聞き、事前に資料を読み込んで業務にあたりました。何事もなく対応が終了した時はほっとしました。 |

| Q8. | 報道に関わる職場なので不規則な勤務時間のイメージがありますが、実際はいかがですか? |
| 私が所属している回線センターの業務は勤務時間が固定されていて残業は滅多にありません。
担務によって出退勤の時間が違ったり、泊まり勤務もあったりと慣れるまで体調を整えるのに苦労しました。 1ヶ月に数日程度、休日出勤が発生することもありますが予定に合わせて別日に代休を取得しています。 勤務の希望は前の月の月初めに提出するため前もって予定を決めておく必要があります。私は半年に1回まとめて1週間程度、有給休暇を取得しています。 |
| Q9. | 休日の過ごし方を教えてください |
| コロナ禍も落ち着いてきて、好きなアーティストのライブを観に行きます。地方公演にも足を運びますが、泊まりがけで行く場合は時間もたっぷりあるので、ライブ会場近辺の観光もしています。 その他にも、周遊型謎解きゲームにも参加し、街歩きをすることも好きです。 予定がなければ、自宅でYouTubeを観て過ごすことが多いです。 |

| Q10. | 就職活動中の学生の皆さんに一言お願いします |
| 就職活動中は周りと比べてしまって気が滅入ることが多いと思います。一度、就職活動を忘れて程よく息抜きをして気持ちを切り替えることが大事です。 就職するにあたって仕事内容なのか、福利厚生なのか、何を一番大事にしたいのかをよく考えて会社を選ぶことが一番だと思います 。 |